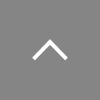看護を基盤にした国際協力への道
中学生のころ、途上国の保健医療の課題を知り、貧困や医療施設、人材の不足などから赤ちゃんやお母さんが適切な医療を受けられず、命を落とす現実に衝撃を受け、看護師だった母の影響もあり看護の道に進むことを決めました。国内で5年間、看護師として経験を積んだ後、JICA海外協力隊の看護師隊員としてホンジュラスで2年間、コミュニティにおける健康に関する啓発活動を行いました。その際、同国でアイ・シー・ネットがJICAの技術協力プロジェクトを行っていたことから、医療現場への支援だけでなく医療システムそのものも改善するコンサルタントの仕事に関心を持つようになりました。
帰国後はグローバルヘルスや公衆衛生について学ぶため大学院へ進学した後、インターンを経てアイ・シー・ネットに入社しました。看護師として被災地や途上国で医療支援をする道も考えましたが、現場で患者さんと関わっているだけでは成し遂げられない、根本的な保健システムや政策を変えたいという想いが強く、開発コンサルタントになる道を選びました。
アイ・シー・ネットでの仕事
JICAの技術協力プロジェクトでは、ホンジュラスの非感染性疾患対策(高血圧・糖尿病)や、パキスタンの母子継続ケアに関するプロジェクトに従事しています。ホンジュラスでは、患者や住民向けに啓発活動に取り組んでおり、パキスタンでは妊婦や乳児が適切な治療を受けられるような仕組み作りをしています。
日本で看護師・保健師として働いていた現場経験や日本の医療システムを知っているということは、こうしたプロジェクトに大変役立っています。なかなか改善が進まないこともありますが、現場に入り込んで、地道に活動していくことの大切さを感じています。
また、最近ではJICAの民間連携事業で医療関係の企業の海外展開も支援しています。ODAのプロジェクトとは違うことも多いですが、社会課題解決という目的は同じですし、日本が持つ良いものを世界に広げていくことにやりがいを感じます。
未来のこと
保健分野にも色々なテーマがあるので、日本で看護師として実務経験をしてきたからこその強みも活かして、専門家としての幅と深さを広げていきたいですね。中でも関心の高い非感染性疾患や保健システムの専門性は一層深めていきたいと思っています。そしてゆくゆくは、プロジェクトマネージャーとして、途上国の保健医療を良い方向へリードしていきたいです。
途上国で働くことの楽しさ
父親が農業系の研究者だったことが影響し、大学と大学院で農業機械を研究していたのですが、1年間ケニアのナイロビ大学農学部で研究する機会がありました。基礎研究が多い日本に対して、ケニアでは実際の農作業で必要とされている技術や機材を開発することに重きが置かれていました。研究が直接農業生産現場の発展につながっていくのが面白く、帰国するころには、またケニアに戻ってこようと思いました。現地の人々の明るさや素朴な感じに魅せられたことも大きいですね。その頃、社会課題を解決したいという大それた強い意識は全くなく、アフリカで仕事することが楽しそうだな、と単純に思い、途上国と関わるキャリアへ進むことになりました。
アイ・シー・ネットでの仕事
前職までは自分の専門性を磨くことを重視していました。アイ・シー・ネットに入社してコンサルタントは売上を上げることが必要で、そのためには自分の専門分野だけではなく、いろんなプロジェクトに対応できる知恵と術が必要であると気づきました。当時、先輩から「カメレオンになれ」と激励されました。それは、自分の専門性を本来の色としつつも、プロジェクトに合わせて色を変化させるカメレオンのような対応力をつけなければならないということです。色を変えるために様々な研修を受け、少しでも対応できそうな案件に積極的に応札してきました。これまで関わったプロジェクトは自分の専門にこだわらず、営農・農業普及・農業一般・流通・マーケティング・零細小企業・コミュニティ開発・農村開発など多岐にわたります。ただ、気がついたら専門である農業機械やコメの収穫後処理技術についてもクライアントから声をかけていただくことが多く、結局自分の専門を生かせるプロジェクトにも関われているのでありがたいなと思います。
農業分野のプロジェクトは稲作、野菜、畜産、農産加工などサブセクターが数多くあり、それぞれに専門性が必要なため1社だけで対応することが難しいことがあります。そんなときは、他社に声をかけて一緒に実施したり、逆に他社から一緒にやろうと声をかけられたりすることもあます。日ごろから他社との社外での緩やかな付き合いを維持しており、その関係性で仕事に繋がることがあります。
未来のこと
これまで経験してきた分野に加えて、最近求められている農産物流通やフードバリューチェーンへの対応力を高めていき、長く農業プロジェクトに携わっていけたらいいなと思っています。自分はODA事業に育てられてきました。これからもこのODA業界に関われたらと思っています。
国際協力への興味
UNESCO憲章の「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」という言葉に影響を受けたことがこの業界を志したきっかけです。人を通じて世界を変えていくには教育が重要だと思い、大学では国際教育を専攻しました。
大学在学中にNGOが実施していたアンゴラの子どもたちを支援するプロジェクトに参加し、その縁で大学卒業後も同じNGOに就職しました。5年間みっちりアンゴラの現場で活動したことで、ポルトガル語が鍛えられたのはもちろん、自分は誰よりもアンゴラに詳しいという自信にもなりました。この専門性を活かしてODAでアンゴラの役に立てればと思い、JICA初のアンゴラ技術協力プロジェクトを受注したアイ・シー・ネットに入社しました。
アイ・シー・ネットでの仕事
最初はアンゴラという国とポルトガル語が自分の専門性でしたが、農業や水産などほかの分野のJICAプロジェクトで経験を重ね、自分の専門性を広げてきました。関わってきたスキームについても多様で、自社企画としてロヒンギャ難民を受け入れるホストコミュニティ支援プロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディングで資金調達したり、JICA草の根技術協力事業へ繋げたりしました。最近では日本企業の海外展開支援として現地調査を実施するなど、多様な事業に関わることができています。国や現場が変わってもクライアントに価値を提供できているのは、これまでの現場経験があるからこそだと感じています。
未来のこと
私に限らずアイ・シー・ネットの管理職に共通することですが、管理職になっても現場を離れる気はなく、今後も現場で活動したいと思っています。ただ、自分ができることには限りがあるので、社員一人ひとりやチームへのサポートを通じてプロジェクトを成功させることで、間接的に受益者の役に立ちたいとも考えています。
国際協力への想い
大学で日本語教育を学んでいたころ、スタディツアーでネパールやカンボジアへ行ったのですが、日本の子どもたちと同じかそれ以上に、現地の子どもたちが楽しそうに学校に通っている姿を見て、衝撃を受けました。一方で、授業や教材には課題が多いと感じ、自分に何かできることがあるのではと思い、国際協力業界に関心を持ちました。
大学卒業後に参加したJICA海外協力隊では、教師として知識・経験が足りず、力不足を痛感する毎日でした。帰国後は、教師として経験を積みたいと考え、日本の小学校で勤務し、外国につながる子どもたちの学習指導を担当しました。日々の仕事を通じて、教師の職能開発における授業研究や知識の共有の重要性を感じ、研究を通して知見を深めたいと考え、大学院へ進学。卒業後は、今までの経験を生かして、現場の最前線で教育開発にチャレンジしたいと思い、開発コンサルタント業界への就職を志望しました。
アイ・シー・ネットでの仕事
入社してすぐにパプアニューギニアの教員養成校で使用する算数教材を開発するプロジェクトに関わらせてもらいました。現地ではより良い教材を作るために議論を交わすところから、実際に教材を使った授業の実施まで、現地の教育省の職員や先生たちと思考錯誤しながら進めます。すべての現場で、現地の教育省の職員や先生たちと額を合わせて、日々悩んだり、学んだりしながら、様々な壁を一緒に乗り越えていくことが最高に楽しいと感じています。
バングラデシュのプロジェクトにも関わっていて、こちらでは業務調整を担当しています。資金管理、契約管理、現地スタッフのマネジメントなど、大変なことも多いのですが、将来、自分が総括になった時に必要な知識を現場で経験を積みながら勉強する機会をいただいていると感じています。
ODA事業以外では、研修講師もしています。オンラインツールの活用やファシリテーションの工夫などのノウハウは他の業務でも活用できますし、研修で扱うロジカルシンキングや調査手法などをODA事業で実践することで、研修講師としても研鑽を積むことができています。
未来のこと
途上国の教育分野の社会課題を解決するため、民間連携などODA事業以外のスキームも活用して、多角的にアプローチしたいです。また、パプアニューギニアに移り住んで全身全霊をささげて現地の発展に貢献している先輩社員を見てきたので、自分も同じように現地に第二の故郷を見つけて、腰を据えた活動をやってみたい、と密かに思っています。